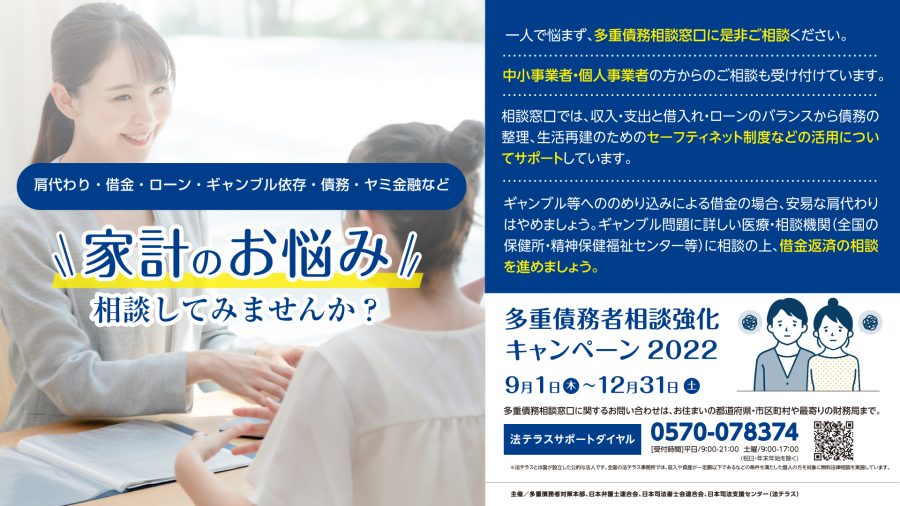11月20日に高知競馬場で行われた能力検査では、上山競馬場からの移籍馬が11頭合格を果たした。
レッドシャトー
4歳牡 中央未勝利の後、上山で6戦6勝という注目馬。D級へ
トウホーゼアス
9歳牡 中央未勝利、上山では70戦14勝。B3まで勝つ。E級へ
スーパーロード
9歳牡 中央~新潟~上山。C2までの勝ち鞍で18勝。E級へ
ニホンカイマリノ
8歳牝 御馴染みニホンカイローレルの娘。益田では日本海特別を2勝。B級へ
カツヤマリュウホー
9歳牡 岩手デビュー、中央での活躍も見せた古豪。D級へ
リンデンアトム
7歳牡 佐賀ではデビュー8戦で6勝。上山C2勝ち。F級へ
トップガン
4歳牝 川崎デビュー馬。なんとか初勝利をの想い。F級へ
ハイフレンドゲイン
9歳牡 中央を振り出しに115戦のベテラン。F級へ
ゼンノペッパー
7歳牡 弟は宝塚記念のダンツフレーム。唯一の白星は障害戦。F級へ
ゼンノタカモク
8歳牡 中央1800Dを1勝。上山A級は不振も。F級へ
トミノクイン
3歳牝 岩手デビューで初勝利が上山だった。3歳戦へ
特筆すべきはレッドシャトーの能検でのレース振り。正に持ったままで後続を引き離し、2着入線馬に1秒6差を付けての圧勝。その時計1分25秒8は相当な水準にあり、同じレースに北海道オープンのナリタサクラオーなども居た中での出色の内容で、今後への楽しみが大きく拡がった。そう、彼らには未来という名の希望があって然るべきなのだ。
なお次回の能力検査でも受検を予定している上山からの移籍馬が多数居るとの情報であり、最終的な高知競馬への移籍数はまだまだ増えそうだ。なんともやり切れない想いはあるが、それでもこうしてやってきた馬達には少しでも長く現役をまっとうして頑張ってもらいたいと願う。
「ふるさと創生」を謳って全国の各市町村に1億円が配られたのは15年前の事だった。当時の竹下内閣がこのような政策を打ったのは下記のような理念の実現のためだったと説明されている。
曰く、東京一極集中が進んで地域格差が拡がっている。今後は地方自治の健全な発展のために、各地域を活性化させ多極化型都市分散国家を目指す。様々な地域を、人々が豊かで誇りを持って自らの活動を展開することができる「ふるさと」として創生することが国土の均衡ある発展のためにも重要である…。
バブル期の話だから今更これをどうこう言わないにしても、かみのやま競馬休止に垣間見える「ふるさと切捨て」とは間逆の方向性を見せていることには改めて隔世の感を覚える。人口3万8千人という上山市が競馬場再建の道を選ばずに、どうにかこうにか理屈を付けて年度内休止に漕ぎ付けなければならなかった背景には市町村合併という裏事情があるのだろう。益田競馬の場合もそうだが、これでは“上山藩のお取り潰し”のようなものだ。この2例の場合は財政再建団体への転落という言葉がキーワードとなったが、果たしてそれが休止理由の切り札として利用されたわけではない確証など誰も示しえないのだ。
競馬関係に従事した人々の数と経済効果を考えれば、少なくとも赤字を削減する方向での存続こそが理性的判断だったように思える。上山という地域(もう単独の市ではなくなる前提なのだろうから)にとっての未来の自立・選択権はすでに奪われ、全国に地域の名をアピールする機会は失われ、馬の居る空間は消滅し、敬われるべき職人達は静かに去る。
美しい自然と共にある競馬場だった。入場口へと連なる街道の見事な桜並木。白く雪を飾り付けた山々。場内実況を担当された與那覇豊和アナウンサーはこの街を心から愛して、冬季には観光案内ボランティアをされていたという。11月11日の樹氷賞の日、與那覇さんは最後までその矜持を失わず自分の仕事を勤め上げた。レース後の阿部市長の挨拶の部分まで司会を担当されていた。
大先輩に対して失礼な表現になるが、とても立派な態度だった。
「ふるさと」は滅びなければならないのか。“構造改革”という号令も“ふるさと創生”のように虚ろなものとなるのか。なぜ15年前とまったく正反対のベクトルが生まれているのだろうか。それを当局は「止むを得ない」と表現する。「止むを得ない」という言葉に潜む無責任極まりない態度を内省的に捉えた事はあるのだろうか。太平洋戦争を描いたある映画に出てくるセリフはこうだ、「(戦争は)止むを得ないで始まり、止むを得ないで終わるのか…」。
日本が経済的に後退した事は確かであり、膨大な国・自治体の借金や、その他にも少子高齢化による今後の社会福祉・年金など未来を悲観したくなる問題が多いのも事実だ。これらの事象を並べて日本の将来に対して諦観にも近い意見を述べるのは簡単で、明るい将来像を導き出せという方が難しく見える。しかしこれらの問題に直面した例は、別に歴史上初めてというわけではない。
例えば“バブル崩壊”ならイギリスでは1700年代に経験済みで、これは南海泡沫事件といってスペイン領南米地域との交易経営を名目に設立した南海会社の株式が暴騰後暴落したものだ。元々が国債の処理に窮した政府によって国策として作られた組織だけに危うさを孕んでいたのだが、巨額の国債を引き受け続け、一方で株価上昇を意図的に煽った結果見事に破綻。ロンドンでは投機熱にうなされ踊った人々が次々と破産、町中に失業者が溢れたのである。政府が率先して行った出来事に恐らくイギリス国民は“鍛えられた”に違いない。
あくまでも自己責任を標榜する大人の社会はこうして出来上がっていく。
少子高齢化は西側先進諸国はそのほとんどが通過してきた問題であり、ある意味1980年代という未曾有の繁栄期を経験した日本が避けて通れない宿題のようなものだ。フランスでは1930年代、ドイツでも1970年代には出生率の低下と福祉の高負担にあえぐという時期を経験しており、いずれもその後に出生率が上昇するなど改善が見られ、成熟した社会への階段をひとつ登っている。
つまりは今後の日本について過度の悲観論を展開するあまり「止むを得ない」と断じてしまうことは思考停止であり、なおかつ歴史の教訓をまたしても生かせない愚挙とはならないか。厳しい情勢の中でこそ知恵を絞り、血ではなく汗を流して努力する事が求められるはずだ。なおかつ問題なのは、勝ち組が負け組を切り捨てる事で、既得権益を守ろうとしているように見える点だろう。そしてそれを誘導する際にも「止むを得ない」という表現が使われる。
歴史学者、あるいは国際政治学者としても名高いアーノルド・トインビーはその著書「歴史の研究」の中でこう言う。
- 人間の、跡をたつことのない欠点の一つは、自分の失敗を、人力ではいかんともしがたい力のせいにすることである。このような考え方は、衰退期の感じやすい人々のとくに魅力を感じるものであって、ヘレニック文明の衰退期においても、なげかわしいけれどもどうしてもくいとめることのできない社会的衰退を、あらゆる面に浸透する「宇宙的老化」に付随して起こる避けがたい結果と説明するのが、諸派の哲学者の通説であった -
つまり社会の衰退について「止むを得ない」を前提に議論する事を“したり顔”をしてしちゃうんだよな、という痛烈な批判である。今の日本にも堂々と通用する皮肉だろう。ちなみにトインビーは日本が戦争に突入してしまった背景を、イデオロギーや民族主義などの飾りを全て取り払った上で、「江戸時代に2000~3000万人だった人口が、明治期以降に急増したため」と分析する。それまでの西洋史観を投げ捨て、洋の東西を問わずこういった歴史への考察を進めたトインビーはある意味予言者的な扱いをされることがある。冷徹なその観察眼は、歴史学上では忌避されてきた「歴史は繰り返す」という事象の存在を示唆しているのだ。彼は文明の興隆と衰退について多くのページを割き、日本のような国際社会において“若い国家”に警鐘を打ち鳴らす。
日本の社会を覆う悲観論は、現状の厳しさに早くも音を上げて「ふるさと」を切り捨てさせる。「止むを得ない」というわけだ。イギリスの“鉄の女”サッチャーは長らく猛威を振るった英国病を治療した。それは政治のパワーバランスを超越した国家としての自浄作用が働いたからなのだろう。日本で同じような難局を乗り切る政策は実現しないのだろうか。中・長期展望に立った実のある政策論争もなしに「政治に関心を」という呼びかけは空しい。
現状認識と、それに伴う「止むを得ない」論理はなるほど一見理性的に思わせる。例えば先に上げたかみのやま競馬の存廃問題だ。しかし本当に上山という地域にとってベターな選択であったかは甚だ疑問である。筆者には当の市長でさえその選択がベターでないことが分かっていたように思われる。ただし選択肢がなかった≒「止むを得なかった」のだ。
日本の競馬社会でも、最近は「香港型競馬に移行するのは止むを得ない」という声がある。つまり、馬産を止めて輸入馬だけによる競馬を、という意味だ。
経営危機に陥っている地方競馬や馬産地を切り捨てるのは止むを得ない。大都市部の少数の競馬場だけでやるならば何とか経営は成り立つだろう、という理屈である。日本の競馬の将来像としては消極的に過ぎる…のだが…。
これはもちろんベストでなく、ベターですらない。
筆者は繰り返し、競馬事業が規模縮小によって生き延びるという実験の失敗、を訴えてきた。輸入馬による競馬が現在と同等の売上げ規模を保てるはずがない。規模縮小は更なる下降スパイラルを辿る。こうなったら衰退は急速にやってくる。日本の競馬はとにかくコストがかかるようにできている。巨大装置産業である本質は恐らくどこまで行っても変わらないから、一定の規模を維持できなければ待っているのは競馬全体のクライシスだ。
相当数の競馬関係者が全体として生き延びる道を、と模索しているのも事実。
手の入れられる部分には改革を進めて、馬産地と地方競馬を残さなければ将来がなくなると真剣に考えている。そのための取り組みが本気で始まったと思われる時期もあったのだが、再び「止むを得ない」論が台頭しているムードを感じ、憂慮せざるを得ない。
例えばプロ野球の発展の為には小学校・リトルリーグ・中高校・大学・社会人野球の存在が不可欠である、という理屈は競馬関係者以外の人にも簡単に理解できるため、競馬において同じ考え方がなぜ出来ないかを説明するのにいつも一苦労だ。そんな時に筆者はやや時間を掛けて登場人物を紹介しなければならない。
日本中央競馬会
地方競馬各主催者
地方競馬全国協会
全国公営競馬主催者協議会
農林水産省
総務省
日本馬主協会連合会
全国公営競馬馬主連合会
日本軽種馬協会
大手生産者及び生産者団体
競馬マスコミ及びジャーナリスト
我が国の競馬のあり方に係わる有識者懇談会
参議院競馬推進議員連盟
地方競馬を持つ中の10道県の首長
競馬について何らかの会に名を連ねる政治家の皆さん
いや、やはり登場人物の多さは特筆もので、ここには書ききれないほどだ。それぞれに思惑があり、利害は一致しない。また力の強い方が政治力を持つ。
しかしあくまでも、競馬が繁栄してこその利害であることをそれぞれが忘れてはならない。だからこそ、空虚な「止むを得ない」理論におぼれることなく、叡智を結集して新しい競馬の形を生み出して行って欲しいと強く願う。
トインビーはこうも言っている。
- われわれは衰退した文明が死に遭遇したのは、刺客に襲われたからではないということを証明したが、しかし、それらの文明が暴力の犠牲となって倒れたという主張に異論を唱えるべき、なんらかの理由も見出さなかった。そして、ほとんどあらゆる例において、自殺の判定を下した -